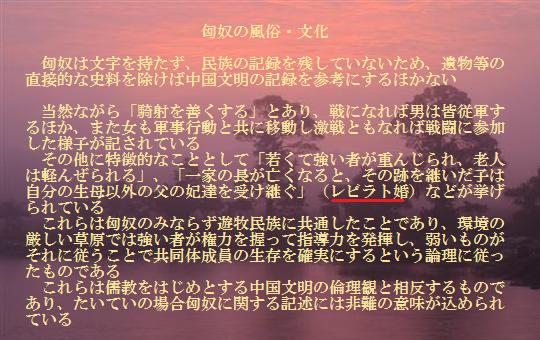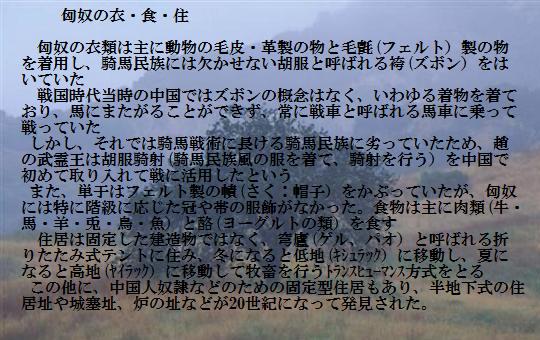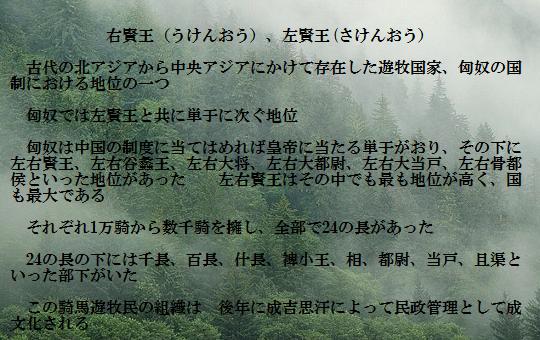= 騎馬民族との融和に嫁いだ皇紀 =
香妃と文成公主 (前編)
カシュガルの阿帕克和卓麻扎(アパク・ホージャー・マーザー) 複合体で 中心をなす、最大の建物であり、最も重要な建築作品であるアパク・ホージャー廟は 私には側壁が妙に落ち着きがなく感じられる。
この廟は、ムハンマド・ユースフが 1670年に、自身の廟として創建したもので、その時 息子のアーファークは まだ 45歳であったが、
父の死後に跡を継ぐと 正嗣子の方が有名になり、1694年に世を去ると この廟を拡幅して、彼も この同じ廟に葬られている。
以降、 この廟はアパク・ホージャー廟と呼ばれるようになった。 私の側壁への違和感はこの為かも知れぬ。
ムハンマド・ユースフの一族もここに葬られたので、その総人数は 5代にわたる 72人、堂内に 現在残る墓碑は 58を数えられる。
また、この地方では 香妃墓(シアンフェイ・ムー)とも呼ばれていますが、墓碑の一つが、清の第 6代皇帝、乾隆帝の妃であった 容妃(イバルハシ)と混同された為です。
この地方、特に 南方のヤルカンドの人々は 熱狂的な香妃ファンで史実は史実として認めながらも、香妃は乾隆帝の慈愛で
死後 124名の衛兵が三年半の日時を費やて 北京から 父の下に嘆送したと信じているのです。
72歳を過ぎた井上靖さんも 香妃ファンでしょう。 この地を訪れ、ヤルカンドまで足を伸ばし、案内してくれるウイグルの美形を“香妃”の再来と錯覚するさまの狂信ぶりを 見事な作品に仕上げています。
されはともかく、“香妃/容妃”(イバルハシ)は肌に棗(ナツメ)の花の香りがあった。
カシュガルは、古代には疏勒国の国都であった。 タリム盆地周辺には古くからトカラ語系の人々が住んでいた。
彼らはコーカソイドではない。 彼らが建国した政権は多く、疏勒国もそのひとつです。
匈奴が強盛の時代には その間接支配を受けたが、中国が統一され、漢が西方に進出して西域都護府を設置すると、その勢力下に入った。 (紀元前二世紀の頃)
その後、漢の勢力が後退すると、柔然や突厥など北方民族の間接支配下に落ちたり、唐が安西都護府を設置すると、安西四鎮のひとつである疏勒都督府が置かれ、その支配下で閉塞していた。
疏勒はタリム盆地南部を通るシルクロード南路の要所であり、この地を訪れた唐の玄奘は疏勒を仏教が盛んな国であると記述している。
12世紀、蒙古族のテムジンがれのジンギスハーンとして蒙古高原の支配者に推戴され、彼の帝国はユーラシア大陸の東部から小アジアまで及び、インド地方を除く大モンゴル帝国と成った。
モグリースターン・ハン国(東チャガタイ・ハン国)はジンギスハーンの正嗣次男のジャガタイの血脈であり、騎馬遊牧民族の征服王朝である。
チャガタイの系譜を引く、トルファンの支配者・アヘナの子サイードが 1514年に カシュガルでハン(君主)位に就いた。 建国の祖・チャガタイ以降 チャガタイ・ハン国は大モンゴル帝国の皇位継承に絡む内紛が続き、
その影響を受けたチャガタイ・ハン国も内部の権力闘争は絶えなかった。 内紛の結果が東西への分裂であった。
西チャガタイ・ハン国ではイスラーム教徒が台頭し、イスラーム文化がタリム盆地に押し寄せていた。
西チャガタイ・ハン国の蒙古王族・貴族たちは 草原の遊牧生活を忘れ去り、各地の封建領主の生活に満足している凋落ぶりであった。
サイードが立位したのは こうした時代であった。
サイードは カシュガルの南南西約300キロのヤルカンドに定都した。
国政の中心をヤルカンドに設けた事で、ヤルカンド・ハン国と呼ばれ、ジンギスハーン一党の王国です。
その勢力は次第に拡大し、タリム盆地一帯の主要なオアシス都市だけでなく、最盛期には天山以北のバルハシ湖南岸や パミール高原以西のフェルガナ盆地にまで 勢力は及んだ。
しかし、統治集団内部の権力闘争や 何時しか浸透したイスラム教の黒山派と白山派の教派対立によって衰え、1680年に モスレム(イスラーム教徒)のムハンマド・ユースフが政権を確立していた。
サイード政権が また チンギスハーンのチャガタイ政権が この地を統治する以前、このタリム盆地はウイグル族が支配していた。 三世紀中頃 古代の疏勒国が、唐に解体させられた以降のことです。
751年7月から8月に掛けて、中央アジアのタラス地方(現在のキルギスタン領内)で 唐とアッパース朝の間で “タラス河畔”の戦闘が行なわれた。
西部へ西部へとその勢力を拡大する唐帝国、東部へとコーランと剣で領域を伸長させるアッパース朝。
唐は この“タラス河畔の戦い”で敗れ、パミール高原の東部域に後退した。
その後、蒙古高原に巨大な帝国を確立したウイグルに追われたモンゴル草原の勢力・カルルクが唐の勢力下で地番を築いて行く。
他方、“安史の乱”(755年)で唐を支援し 漢中に勢力を伸ばしたウイグル帝国は唐帝国を併呑しようとするが、天災と疫病の発生 また 内部闘争の虚をキルギスに突かれて崩壊した。
ウイグルの王族とウイグル人が大挙して、西に逃走した。 そして、9世紀の初頭には カルルクをパミール高原の西部域に追い落とし、また 土着のトカラ語系民族と混血し、天山ウイグル王国を建設した。
10世紀には、最初のテュルク系イスラーム王朝であるカラハン朝の勢力が パニール高原を越えてカシュガルに延び、カシュガルは、その王都となって 天山ウイグル王国と対峙していた。
唐はタリム盆地から撤退し、漢中は五胡十六国時代に変わっていた。
タリム盆地から漢中の勢力は消えるが、カシュガルの城市は 宋代には契丹族が建てた西遼に属し、元代にはチャガタイ・ハン国の陪都となり、明代には 上記・ヤルカンド・ハン国に属していた。
このような歴史のなかで カシュガールは、イスラーム化したウイグル人の中心的都市と変化していた。
清代に入ると、乾隆帝の新疆征服により、カシュガル直隷州が設置され、新疆南部を統治する参賛大臣が駐在した。
乾隆帝は戦いを好む皇帝であった。 清の第6代皇帝に即位したのは24歳。 1735年10月8日 に戴冠している。 皇帝として、領土を拡大して行った。
10回の外征を行なっている。 ジュンガル、雲南の金川、ヒマラヤ南麓のグルカに2回ずつ、回部、台湾、ビルマ、安南に1回ずつ計10回の遠征を“十全武功”と言って誇り、自分を十全老人と呼んでいた。
1736年の春、“香妃/容妃”はヤルカンド・ハン国の国祖・ムハンマド・ユースフの子であるアパク・ホージャーの孫そして生を受けた。 四代目の皇女として生まれた。
当時、ヤルカンド・ハン国は清朝に統治権を奪われ、毎年 清朝に貢賀し、燕京(北京)には強制使役に駆り出されたウイグルが多く滞在し、
また シルクロード交易に携わるウイグルが幾多生活の基盤を設け 回教寺院らしき館屋設け、圧政から逃避する拠り所にしていた。
花香る姫に成長した“香妃/容妃”は パミル高原から流れ来る莎車(ヤルカンド)川の川原が好きであった。 遠く天山山脈の雪嶺を望み、莎車(ヤルカンド)川の冷水は真夏でも砂漠を忘れさせた。
しばしば、襲い来る凶悪な竜巻すら、彼女には自分を守ってくれる守護神の使いだと思っていた。
いつしか “香妃/容妃”が発する棗(ナツメ)の花の香りが、彼女の美しさに輪をかけて 疆南部を統治する 清朝の代理人・参賛大臣の耳に入った。
1756年、乾隆帝は第二回目のジュンガル征圧の親征を行なった。
ジュンガル地方は完膚なきまでも破壊され、ジュンガルのオイラト・モンゴルやウイグル人で生き残った者はロシアや南方の莎車(ヤルカンド)・ホータンに逃散した。
≪ このジュンガルのジェノサイトは 紀行記“草原の道”・“最後の騎馬遊牧民国家・ジュンガリア”に 記載済み、閲覧下さい ≫
閉塞するヤルカンド・ハン国第四代君主は、莎車(ヤルカンド)城市に逃げ来る逃亡者を匿い、参賛大臣の目をごまかし 支援の手を差し向けたが、参賛大臣はこれを咎めた。
翌年になり、婚期の遅れていた“香妃/容妃”の婚儀が進められている中、
参賛大臣が新春の貢賀の折に“香妃/容妃”を伴ない、燕京(北京)宮廷に参内する旨 厳命した。
1760年、“香妃/容妃”は22歳、乾隆帝は49歳であつた。 乾隆帝は“香妃/容妃”に魅せられ、直ちに イタリア生まれのイエズス会の宣教師である絵師・ジュゼッペ・カスティリオーネに彼女の容姿を描かせた。
“香妃/容妃”は第15位の皇后として、以降28年間 乾隆帝の寵愛を受けている。
“香妃/容妃”は、燕京(北京)に住むウイグル族・イスラーム教徒の安住が確証されるまで 乾隆帝を拒み続けたと言う。
北京市内にあるモスク(回教寺院)の清真女寺・ 牛街礼拝寺などは宋・明時代の建立ですが、朽ち果てた寺院を修復し、名刹としたのは彼女の力でしょう。
1788年 “香妃/容妃”(イバルハシ)は54歳の時、病に倒れた。
彼女の遺体は 124名の衛兵が三年半の日時を費やて 北京からカシュガル 父の元に帰国したと “香妃ファン”は信じて、疑わない。 シルクロードのロマンです。
乾隆帝は 1796年2月9日に崩御した。 彼は“十全老人”と自称する武将であり、“文字の獄”と呼ばれる思想弾圧で多くの人々を処罰し、
禁書も厳しく実施した独裁者であったが、欧州列強を見据えた清帝国の確立者でもあった。 順治帝・雍正帝・乾隆帝と清帝国の全盛期は幕を閉じ、
愛新覚羅・溥儀(アイシンカクラ・フギ)がラスト・エンペラーとして最後の幕を切り落とした。 清朝皇帝の終焉は 1912年2月12日の事です。
尚、乾隆帝の陵墓は清東陵内の裕陵。 だが、中華民国期の1928年に国民党の軍閥孫殿英によって東陵が略奪される事件が起き“東陵事件”、
乾隆帝の裕陵及び西太后の定東陵は、墓室を暴かれ徹底的な略奪を受けた。 “香妃/容妃”(イバルハシ)も この陵墓近くに眠っていたと言う。
この事件は溥儀にとっては1924年に紫禁城を退去させられた時以上に衝撃的な出来事であり、彼の対日接近への布石にもなったと言われる。
ソンシェン・ガンボ(581年頃 – 649年)は、古代チベットの王。 伝説上では33代目とされるが、事実上の吐蕃の建国者です。
ラサを都として、領域を拡大。 チベット文字を制定し、インドや中国の文化を積極的に取り入れた。
十六清浄人法という道徳律や大小の宝石で十二位階に分けた位階を制定したりと、聖徳太子にも似たところがあります。
また、ネパールから王女ブリクティー・デーヴィー(タクリ王国の王女、赤尊公主)を妃に迎え、更に唐の太宗に頼んで、皇女の文成公主を息子・グンソン・グンシェン王(在位641-643)の妃に迎えている。
グンソン・グンシェン王が落馬事故死した後、63歳で重祚し、息子の未亡人・文成公主を自分の妃にした。 また、王はチベット人の妃も3人娶っていた。
ソンシェン・ガンボ王は吐蕃を発展させたが、晩年は功臣の処刑が続き、蘇族平定に大功のあった将軍や、蔵蕃を帰順へ導いた謀臣を粛清している。
・・・・・・・ さて 明日は 唐帝国が覇権を確立した太宗の時代にラサに下った皇女“文成公主”の話をしましょう。
彼女はラサに赴く折、頭髪に門外不出の“繭”を隠し持ち、ヒマラヤ近隣に絹を伝えたと言われています。
_____ 続く _____
*当該地図・地形図を参照下さい
—— 姉妹ブログ 一度、訪ねてください——–
【疑心暗鬼;民族紀行】 http://bogoda.jugem.jp
【浪漫孤鴻;時事心象】 http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/
【閑仁耕筆;探検譜講】 http://blog.goo.ne.jp/bothukemon/
【壺公慷慨;世相深層】 http://ameblo.jp/thunokou/
※ 前節への移行 ≪https://thubokou.wordpress.com/2013/06/29/≫
※ 後節への移行 ≪https://thubokou.wordpress.com/2013/07/01/≫